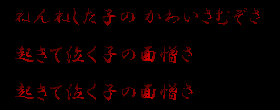
唄が聞こえた。
これは、子守唄。
白い着物を着た女が匣を抱いている。
儚げで美しい横顔。あれは、久遠寺涼子だ。
匣、匣の中には、
少女が、
手足のない少女がこちらを見て、

嗤った。
黒百合の章
関口は眩暈坂を、死にそうなほど懸命に走っていた。
けれど足は進まない。ずぶずぶとまるで土の中に足が埋まっていく錯覚すら覚える。
見慣れたはずの京極堂が遠い。息が上がっている。私はひどくみっともない生き物だ。
そう自覚しながら、それでも関口は手に握りしめた紙片を届けるために懸命に走る。
愚鈍な猿がいくら走っても頂上には辿り着かぬのだ、そう脳の中で誰かが嗤う。
それでも行かねばならぬ、と関口は言う。
無駄だ無駄だと誰かが嗤う。
それは関口の中でやがて形作る。嗚呼、こいつは久保だ。
久保が私を嗤ってゐる。
けれど私は行かねばならぬ。
そう、私はメロスだ。
走らねばならぬ理由がある。
二度と過ちを繰り返さぬ為に。
あの夏の過ちを。
「関口!!」
坂の上で誰かが関口を呼んだ。
汗だくの顔を上にあげる。それすらしんどい。
「だ、だんな・・・・木場修・・・」
弱弱しい声で木場に手を伸ばす。
木場は関口の手を、その手の中にあった紙片を乱暴に奪い取った。
それを一瞥し、木場の形相が鬼のように変わる。
「畜生!」
木場は紙片を関口に押し付け、坂をかけていく。
嗚呼、メロスだ。
関口はひとりごちる。
私の役目は終わったのか。
「まだだよ」
関口の心を見透かしたかの如く、坂の上から鬼の声がする。
鬼はひどく険しくまるで地球上全ての生物が死に絶えてしまったかのような顔つきで立っていた。
その鬼に向かって再び手を、伸ばす。
「木場の旦那は今朝方急な呼び出しが掛かって警察に行かなければならなくなった。
だから今朝僕に電話があった。僕は彼女を二時に迎えに行くと言った。
そして木場は二時に僕が迎えに来るからそれまで此処にいろ、と伝言を残したのだ」
鬼は眉に皺を寄せ、紙片を握りつぶした。
大事な証拠だろう、そう言いたかったが言えるはずもなかった。
「すりかえられたのか・・・・・」
「その通りだ」
「でも、彼女は、」
御筥様の信者でもなければ、もう少女でもない。
被害者はいずれも若い少女だったはずだ。
何故、犯人は彼女の存在を知り得たのか。
何故、犯人は彼女を攫ったのか。
私だけではない、
木場も、榎木津も、そして京極堂も、そう思っているんじゃないだろうか。
「とにかく今は君の身の安全が第一だ。それについては木場の旦那に任せるしかない。
それと榎木津だ。あいつも行ったんだろう」
「けど、榎さんは・・・ただ闇雲に走って行っただけだ」
「あいつにしか視えないものを視たんだろう。だったら心配ない」
京極堂はそう言うとそのまま踵を返した。
ざくざくと下駄が土を蹴る音が響く。
「待てよ!君は・・僕達はちゃんを探さないのか!」
「探すと言って何処を探すんだ。いいかい、関口君。人には役割というものがあるのだ。
僕には僕の、関口巽には関口巽の役割がある。木場と榎木津はそれを果たしに行ったのだ。
僕は僕の役割を果たす。それだけだ」
なんだというのだ、その役割というのは。
私はそれを知りたいのだ。
けれどこの男は最後の最後までそれを言わぬ。
果たして初めて、それが役割
この男は犯人を知っているんじゃないのか。
「上に鳥口と、もうすぐ青木君が来る。君も聞きたくば聞けばいい」
「なにをだ」
「決まってるだろう、例の武蔵野の事件だ」
「武蔵野・・・・じゃあ、やっぱり、」
「やっぱり?なんだね」
京極堂が怪訝な顔をして片眉を釣り上げた。
知っているんじゃないのか、犯人を、その言葉が喉から出ない。
白い手袋の男を、私は知っている。
私の中のその男はをみっしりと匣の中に詰めている。
バラバラ殺人とあの男とはなんの根拠も無しに私の中で繋がっているのだ。
彼女は匣の外からきた
久保は箱の外を覗いてしまったのだ
そして彼女が箱の外から来た事に気づいてしまった
だから欲した
久遠寺涼子は箱の中に彼女を引きこんだ
だが久保は彼女の中に箱の外があると思っている
久保は彼女で匣の中をみっしりと埋めようとしている
違う、それは私の妄想だ
違わない、久保は彼女で匣を満たそうとしている
ばらばらばらばら、
私の中で彼女が形を失ってゆく。
彼女とは、誰だったか
だったか、
それとも、
久遠寺涼子だっただろうか―――――――
関口は鬼の後を追い、眩暈坂を駆け上がった。
ふと、耳元で、
赤ん坊の泣き声と子守唄が聞こえた気がした。