4時44分44秒の学校のチャイムを聞いてはいけない。
屋上への階段、12段のはずが一段増えて13段になっている。
合わせ鏡の前に立つと異界に引きずり込まれてしまう。
誰もいない音楽室の中からピアノの音が聞こえてくる。
夜な夜な動く美術室の石像。
誰もいないはずのプールで聞こえる水音。
学校のどこかにある絵日記を開いてはいけない。
としでんせつ
「沖田、無事か!?」
「沖田君!シロ!どこ!?」
土方達と別れた山崎とは一階の玄関踊り場まで来ていた。
だがどうしてだろう、二人の姿はなく、辺り一面が黒い靄で覆われている。
尋常ではない様子に二人は焦るが、肝心のメリーさんの姿さえ見えない。
「くそっ!なんなんだ、この黒い靄は!!」
「なにかの現象が起きてる・・・これもヒトガタで封じられるのかな・・・」
「だが、どうすれば」
「シロがいないと封印の仕方がわからない!シロ!沖田君!どこなの!?」
焦れば焦るほどに周りの靄が濃くなっていくように思う。
いや、実際二人はすでに靄に囲まれていた。ただ静かに、ゆっくりと二人を輪の中心に追い詰める。
「「・・・!」」
二人の肩が音を立ててぶつかる。
山崎は手の中の埴輪を握りしめる。これをどうすればいいのか、検討もつかない!!!
靄がゆっくりと二人に迫ってくる。それは二人をからかうように前後左右にと動きまわる。
くすくすくす
キャハハッハ!
ねぇねぇ
ふふふっ
思わず耳を塞ぎたくなるような、気味の悪いたくさんの声。
子供?大人?男?女?その判別がつかないくらいのたくさんの声!
「君!」
靄がの身体に触れそうになった。その瞬間、山崎がを引き寄せ抱きしめる。
それはとても些細な抵抗。無駄な足掻き。無意味無駄無力!!
「さぁ、いっしょにあそびましょう」
たくさんの声の中から、一際大きな声が聞こえた。
それがまるで化け物のように束となって二人に襲いかかる!
「くそっ!」
「きゃあ!!」
「山崎!ヒトガタ置いて伏せろ!!!」
その刹那、だった。
慣れ親しんだ怒号が聞こえて咄嗟に山崎の身体が動いた。
その命令通りに埴輪を床に置き、を腕に抱いたまま、床に伏す。
それはこの場で聞こえるはずのない声。
けれどとても逞しく信頼できる人の声!
「レエカニカナノコハテベスハノモルザラアニノモノヨノコ」
それは誰の声だったのだろうか。
その不思議な言葉が聞こえた瞬間、ヒトガタである埴輪が光り出しその光が黒い靄を照らし出す。
そして埴輪の口がみるみる内に黒い靄に吸い込まれていく!
カタカタカタカタ
やがて光が弱くなり、埴輪がカタカタと揺れた後、その動きが止まった。
山崎がおそるおそる顔を上げると、すぐ傍には総司が同じように地に伏せていた。
「沖田!」
「そんなに大きな声出さなくても、聞こえているよ・・・・」
相変わらずの捻くれた言葉だが、とりあえず無事なようでほっと息を吐く。
「山崎君・・・・封印できたのかな・・・・・」
「ああ、そのようだ」
腕の中のも無事なようで、二人で支え合いながら起き上がる。
そして三人は、あの声の主を見上げた。
「お前ぇら、無事だな?」
「まさか土方さんに助けられるとは思わなかったなぁ」
「土方先輩、どうして・・・・、」
山崎は目の前にいる尊敬すべき先輩と埴輪を戸惑いながら交互に見つめた。
どちらかと言えば、土方は心霊現象や怪談話は否定派だ。無駄話だと一蹴するタイプの人間だ。
それなのにどうして、ヒトガタの封印の仕方を知っているのだろう。
それはその場にいる人間の当然の疑問。
だがその疑問は、土方ではなく、別の人物の口から語られることになる。
「くすくすくすっ たすけてあげたのわたしなんだからね かんしゃしてよね」
「うわっ!」
「きゃあ!!」
さすがの沖田もも悲鳴を上げた。
土方の肩から女の子の顔が覗いたのだ。
しかもただ覗いたんじゃない。その顔は逆さ、つまり天井からぶらさがっているということ!
「・・・っ!」
山崎も言葉が出ないほど驚いて絶句している。
けれど当の土方は呆れた顔で振り返り、その少女に向かって部員達を叱るのと同じようにたしなめる。
「てめぇ、いちいちぶら下がってんじゃねぇよ。こいつらが驚くだろうが」
「あら、わたしもがっこうのおばけだもの。おどかさなきゃいみないもん」
「時と場所と場合を選べっつってんだよ」
「おうまがとき、がっこう、はいごから、すべてそろってるとおもうけど?」
「口応えすんじゃねぇ!!それより、総司、なんだその犬は」
まるで忌々しいものでも見るように、眉間にしわを寄せる土方はいつもの鬼部長そのものだ。
なんだ、と言われた当のシロは沖田の腕の中でハッハッと荒い息を吐いている。
「いや、土方さんに言われたくないんだけど・・・・ほんとに」
「花子を味方につけるたぁ、やるじゃねぇか若いの」
「あん?なんで犬が喋るんだ」
「土方さんこそ・・・その子・・・・花子さんなの?まずそっちから説明してよ」
「ぁあ?こいつは確かにトイレの花子さんだ。この現象の原因を知っている」
「「「!!!」」」
三人は一斉に息を呑んだ。その様子がおかしいのか、花子さんはニタニタといやらしい笑みを浮かべる。
白いシャツにプリーツスカート、いまだぶら下がったままで振り乱された髪に青白い顔。
とても直視出来るような姿じゃない。これならシロの方が大分マシだ。
だがその少女の霊が、この怪奇現象の原因を知っているという。
は思い切って口を開いた。
「貴方の・・・仕業じゃないのね?」
「ちがうわ。だったらとしちゃんもあなたたちもたすけたりしないもん」
「てめぇ、そのふざけた呼び方やめろっつったろ!!」
「やだなぁ、土方さん。ロリコンの上に人外趣味だったわけ?」
「沖田、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。ならば原因とはなんだ?」
「あのこのしわざよ・・・・きっと」
花子さんはそう言いながら、彼女にとっての足元、つまり天井を見つめた。
自然とその場の全員が上を見上げる。だが当然のようにそこには天井のタイルと蛍光灯しかない。
「あの子って誰?やっぱり怪談話に出てくるお化けなの?」
「ちがうわ。あのこはおばけじゃない。でもいきてもいない」
「どういう意味だ」
「わたしもよくわからない。でも、あなたたちがここからでるほうほうはしってる」
花子はぶらぶらと身体を左右に揺らしながら答えた。
どうにも人を驚かしたくて仕方がないらしい。手がわきわきと動いている。
土方はそれを無視して、絵日記帳を取り出す。
「俺達がこのおかしな現象に取りこまれたのは、この絵日記が原因らしい。
俺がこれを拾った時は、花子からのメッセージが書いてあった。
だが今は何も書かれていねぇ。そしてさっき、お前らが襲われていた時には――」
土方は手に持っていた絵日記帳を三人に見せた。そしてそれを開いて見せる。
「ここに呪文が書いてあってそれを花子が唱えた。だが今は・・・・」
「何も書いてないね」
総司がペラペラとノートを捲って確認する。どのページにも何か書かれている形跡はない。
「私、それ図書室で見ました。やっぱり何も書かれていませんでしたけど」
「本当か!?だが俺が見つけたのは2階の廊下だったぞ。お前、それいつだ?」
「図書室にいて、その本が床に落ちてて拾ったけど何も書いてなくて・・・
その時は校庭から声も聞こえて普通だったと思います。そう・・・おかしいな、と思ったのは
図書室を出てから・・・・・、廊下を歩いていたら急に暗くなって」
一つ一つを思い出すように呟くに山崎が気付く。
「そういえば、平助が図書委員の当番から帰って来た時、様子がおかしかったな」
「そう言われると、そうだね。丁度校庭に人がいないって気付いたのも平助が戻ってくる直前じゃなかった?」
「図書室に何かあるのか?花子が言うにはこの絵日記の持ち主を見つけりゃ戻れるらしい」
考え込んでいる時間はあまりない。けれど四人がその場で行き詰って悩んでしまう。
思案する総司の腕の中から抜け出したのは、人面犬だ。
そしてふんふん、と鼻を鳴らし、あちこち匂いを嗅いで回る。
「なぁ、総司よぉ」
「なに。今、忙しいんだけど」
「その平助と千鶴はどこ行ったんだぁ?」
「「「「!!!!!」」」」
その言葉に全員が凍りつく。
総司はてっきり平助達は土方達と合流しているものだとばかり思っていた。
「シロ、平助達は斉藤先輩達と合流出来ていないのか!?」
「ちょっと!土方さん、平助達と会ってないわけ!?」
「会ってねぇ!斉藤達に合流しろと頼んだが・・・・考えが甘かったか!」
全員に視線がシロに集まる。シロは曖昧な顔をして首を横に振った。
「その斉藤ってのを俺は知らねぇが、平助と千鶴の匂いなら覚えてる。
だが二人の匂いを感じねぇ。無事でいるなら、感じるはずだ」
「それって・・・つまりどういうこと?」
が言葉を選ぶように尋ねる。
「・・・・・・手遅れってことだ」
忌々しげに人面犬は呟く。その言葉に全員が息を呑んだ。
手遅れ?なにが?誰が?いつもの日常のはずだった。それなのにどうして仲間が欠ける?
「ふざけないでよ!!どうして僕達が襲われなきゃいけないのさ!!」
「総司!落ち着け!!!」
「どう落ち着けって言うのさ、土方さん!どうして僕達がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ!」
取り乱した総司は土方の胸倉を掴んだ。とっさに山崎が二人を引き離そうとするが、力は及ばない。
「まだたすからないってきまったわけじゃないわ」
その喧騒をいかにもつまらなそうに見つめながら花子が突然くるりと身体を一回転させた。
床に音はしなかったけれど、彼女は手を使って床に着地した。それはつまり逆立ちした状態。
どうしても逆さの状態でいなければならない理由でもあるのか、訝しむ全員の前で土方の手の中の絵日記を指差す。
「ようはすべてをなかったことにすればいいということ。すべてを”ゼロ”のじょうたいにもどせば、あなたたちのにちじょうのなかにこのできごとはなかったことになる」
「でも、どうすればいいの?」
「あのこをふういんする―――――しかないでしょうね。もっともわたしにもあのこのしょうたいはわからない。どうすればふういんできるかけんとうもつかないわ。ただやっぱりてかがりは―――」
「図書室、ね?」
の言葉に花子が頷く。
総司は土方の胸倉から手を放し、小さくごめんと呟いた。
土方はもう一度絵日記を開く。するとそこには四人を嘲うかのように、一つの言葉が書かれていた。
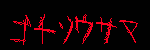
「・・・・・・っくそっ!!!!」
嘲笑っているのか、挑発しているのか、馬鹿にしているのか。
一体それが何を意味しているのか、分からない。けれど嫌な想像はあとからあとから湧いてくる。
土方はそれを振り払うように絵日記帳を閉じると、後輩達を見回す。
部長として、先輩として、一年達を護らなければならない責務が土方にはある。
「花子、俺と一緒に来い。お前らはその犬と一緒にどこかに隠れろ」
「そんな!土方先輩、まさか一人で図書室へ行くつもりですか!」
「ここでまた分散なんて正気ですか?これ以上人数を割くのが得策とは思えません」
山崎、が土方を止めようとするが、土方は聞き入れようとはしない。
そんな土方に総司が嫌味なまでに大きなため息を吐く。
「ほっんと土方さんって馬鹿だよねぇ」
「なんだと!?」
「山崎君はともかく僕がそれで大人しくしているとでも思うわけ?僕は別に土方さんの言うこと聞かなきゃいけない義理なんてないし、勝手に図書室に行かせてもらうよ」
「だよなぁ。お前はそういうやつだぜ、総司ぃ」
ニヤニヤと下卑た笑みでシロが総司を見上げる。花子も面白そうにくくくっと忍び笑いをした。
「ぜんいんでいくことね。そっちのふたりもかくれているきなんてなさそうよ」
花子の言葉に山崎とが頷く。どの道もう、道は残されてはいないのだ。
「ちっ、たくどいつも」
そう言いながら土方の口元はどこか笑っている。
「しょーがねー。四人全員で行くぞ」
「よにんじゃない、ごにんよ」
「あともう一匹足しとけよ」
花子とシロが土方のセリフに不満げに口を挟む。
誰ともなく笑い声が漏れ、それは暗い廊下に場違いに響く。
「じゃあ、五人と一匹ね!行こう!」
希望は捨てない。まだ、仲間がいるから。
全員が四階最奥の図書室を目指し駆け出した後、一階は静まり返り――――――――やがて闇に溶けて何もかもなくなった。
「雪村君!藤堂君!!」
天霧は鏡に向かって何度も何度も呼びかけた。
鏡を叩いても触れてもなんの反応もない。
信じられないことに、天霧と不知火の耳元で子供の声がした直後、子供が千鶴と平助の身体に群がり、その後二人が鏡の中から消えてしまったのだ。
後に残されたのは、正しい世界。
不知火と天霧の他にはなにも映っていない、鏡本来の姿。
それなのに、天霧の悪寒は止まらない。
二人は一体どこへ行ってしまったというのか!
「おい、風間呼んで来たぜ!」
「一体何事だというのだ」
不知火が息を切らせて部屋に飛び込んできた。その後ろには至極機嫌の悪そうな風間がいる。
天霧は果たして彼が自分の言葉を信じるだろうかと思案する。
だがありのままを話すしかない。例えそれがどんなに奇怪な事実であろうとも。
外はもう陽が落ち、漆黒の闇に姿を変えていた。